No.1 医療需要者としての市民と医学教育〜わが国の医療のすがた〜
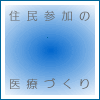 厚生労働省社会保障審議会医療部会委員 佐伯晴子
厚生労働省社会保障審議会医療部会委員 佐伯晴子
昨今、国民の医療に対する目は厳しい。医療費の自己負担増と医療事故の顕在化のもと、「お医者様にお任せしていれば治る」とは誰も考えなくなっている。当然といえば当然のことである.にもかかわらず、医療現場では忙しさと専門知識における非対称性を理由に、患者が理解し納得するという本来のインフォームド・コンセントはなかなか進まず、医療者の判断で診療がとり行われるのが通常である。これまで「お任せ」していた患者の態度も問題であろうが、クリニカルパス、レセプト、領収書など患者のための情報提供が極めて乏しい現状からすると、「お任せ」せざるを得ないというのが事実だろう。
しかし、長年にわたる国民・健康保険料納付者の願いがついに平成18年の医療法改正で日の目を見ようとしている。筆者はこの医療法改正に深くかかわる厚生労働省社会保障審議会医療部会で2年間、患者・国民の立場で検討に参加してきた。患者の立場でもあるが、むしろ現在健康な国民として、あるいは納税者として、社会の重要な基盤(インフラ)としての医療が、国民の総意を反映したものであるのか、安全が確保されているのか、サービスは利用者のニーズを満たしているのか、そこに従事する専門家が能力を十分に発揮できる環境が整っているのか、財源の配分は妥当であるのか、持続可能なコストバランスが保たれているのかなどに大きな関心を寄せてきた。
社会保障審議会医療部会での一貫したテーマは、「患者・国民にわかりやすい医療」および「安全で安心できる医療」である。そのため医療提供体制という制度・組織の枠組みも、従来の形に留まらずに、よりよい医療づくりのためには部分的な撤廃も創設も行われる。
また,わが国の医療が現在どのような状況にあり、その背景には何があるのかをまず国民に知らせることから始める必要があると部会で私は主張した。なぜなら個々の医療の中で問題と感じることの何割かは、個々の医療者と患者との関係以前に、制度上の障害や問題が横たわっていると考えられるからである。
患者や国民から信頼されるため最初に行なうべきは情報提供であり、また実際に行なった医療についての説明責任を果たすことであるという考えには、国、行政、医療者側、患者側のすべてが賛同した。患者・国民が必要とする情報を提供するのは当然のことだろう。当初日本医師会の抵抗があったものの、情報開示は一般社会では常識であり、皆保険制度の存続のためには国民の理解と納得が欠かせないとの判断があったのか、医療制度、医療機関、診療内容とすべてにおいての情報提供が基本的になされるようになる。これは大きな前進であると評価したい。
問題の原因はどこにあるのか
ただ、現在、わが国の医療で何が起こっているのか、ということを実は誰も把握できていないのが事実である。ある疾病について、全国でどの程度の診療が行なわれているのか、施設ごとの治癒率、治療方法、治療期間、使用薬剤、費用など、横断的な調査はこれからということである。疾患ごとに医療水準を設けることが、なぜ今までできなかったのか、要因はいくつかあるだろうが、水準がないために、結局は患者からすると「場当たり的」な診療がなされているように思われる。つい最近も「がん治療」についてのNHKテレビ特集が放映されたが、全国各地で、各医療機関でいかに治療内容にバラつきがあり、患者にとっては「当たり外れ」に近い状態であるかが生の声として伝えられた。
(2006年1月7日,8日放映 NHKスペシャル 「がん治療」)
このような医療の実態には、患者や家族として体験して初めて気づき、やみくもに立ち向うことになる。そしてかなりエネルギーを消耗した段階で、当事者として抱えている問題は個別の特殊なことではなく、わが国全体で起こっている状況らしいとわかり、愕然とするのである。がんの疼痛緩和ケアひとつとっても、WHOプログラムが20年経っても実践されていない、地域内での紹介連携がない、院内での連携がない、医師が知らない、医師の考えが患者の訴えより優先される、など「患者中心の医療」とは程遠い現実であることがわかる。その番組内で国立がんセンター総長の垣添氏は、「今まで医師は科学的な数値を患者さんの主観に優先させてきた。しかし医療というのは実は患者さんの主観に共感することである」と発言し、他の医師も「学校では痛みに対処することは教わらなかった」と医学教育の不備を語った。
「がん治療」は医療全体の中では一部にすぎないであろう。しかし、高齢化とともに、がんを患う人は確実に増えている。ある程度生きているとがんを患うと考えてもあながち間違いではなさそうである。その意味では、誰もがかかる病気、誰もがかかえる問題として、多くの国民がこの番組を見たであろうし、家族をがんで失った人たちは、わが国の医療の実態が20年でさほど変わっていないことに驚きと嘆きを覚えたであろう。私もそのひとりである。1988年から93年まで暮らしたイタリアのミラノでは、ごく普通に緩和ケアが行なわれており、緩和ケアのためのボランティア医療チームと市民グループが組織されていた。北イタリアにおいて90パーセントのがん末期の痛みを緩和するのが常識であったのが、すでに20年以上も前である。その間わが国は何をしていたのか。医療部会に参考人として出席された川越厚医師も、私の疑問に「緩和治療が医学教育の中にないから」と無念の表情で答えられた。
篠原出版新社 医学教育白書2006年版 収載
参考文献:
厚生労働省社会保障審議会医療部会「医療提供体制に関する意見」
(平成17年12月8日)
藤垣裕子「専門知と公共性」 東京大学出版会
小林傳司「公共のための科学技術」 玉川大学出版会
