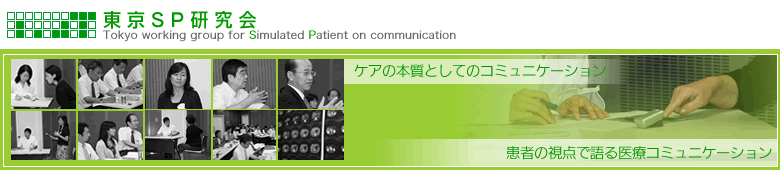東京SP研究会トップページ > ようこそSPの世界へ:佐伯晴子 > 2002年 日本医学教育学会大会 発表
2002年 日本医学教育学会大会 発表
医療面接実習の効果はOSCEに反映されているか
医療面接実習とOSCEのあり方の検討
|
医療面接実習の効果はOSCEに反映されているか
東京SP研究会 佐伯晴子
協力 筑波大学医学専門学群平成13年度4年生 OSCEの実情 東京SP研究会で協力したOSCE 平成13年度 医学科 20大学 のべ27回(2学年) そのうち、SPとの医療面接実習をOSCE前に行っているところ 全員体験の実習 1大学
一部学生の実習 5大学 講義・デモンストレーションのみ 2大学 いずれもなし 12大学 半数以上のOSCEで、 ①学生は初めてSPとの医療面接を体験し、 ②教員は初めてSPの演技や評価方法にふれ、 ③SPは、その大学の教員と学生に初めて出会い評価している |
|
初めての場合に遭遇すること ① SPの扱われ方 何者? 下請け? 協力者? 工事業者? しゃべる人形? ② 医療面接における価値観がSPの「信頼関係づくり」と乖離 医療面接イコール「鑑別診断のための問診」 評価方法は適切か 形成的評価 (褒めすぎる評価者も) 総括評価 (誤解?試験なのでフィードバックをつけない) ⇒良いところも、改善できる点も指摘できない 評価表に記述したことが、どこまで学生さんにフィードバックされるのか心もとない状況がある(評価表の扱い) (なぜSP?) ③ OSCE手順の合意 ・開始と終了の合図 ・学生メモの扱い ・SPのフィードバックの導入 |
|
SPとの医療面接を全員体験した大学におけるOSCEの結果 設定学年 4年生後期(平成13年12月~14年2月) 形態 4グループ(各5名) 一回の実習 3時間で20名が体験 事前準備 医療面接講義 学生同士のロールプレイ(VTR使用) SP実習における注意 「あくまで次回も来院してもらえるように、話が続けられること、関係が 作れることをめざすこと」 時間 7分 (すべてを聞き出す必要はない、途中でかまわない) |
|
OSCE設定 時間 5分間 OSCEの評価表(教員)設定 1.面接の導入 あいさつ、自己紹介 患者確認 面接の環境整備 2.面接技法 最初に患者が自由に話せるよう配慮 患者が話しやすいよう促進 共感的態度 要約 解釈モデル・受療行動を把握 3.態度 視線 適切な言葉遣いと態度 |